はじめに
会社から「従業員持株会に加入しませんか?」と案内を受けたことはありませんか。すでに毎月積み立てをしている方もいらっしゃるでしょう。従業員持株会は会社員にとって身近な資産形成の手段ですが、その仕組みやメリット・デメリットを正しく理解している方は意外と少ないものです。今回は、ファイナンシャル・プランナーと投資家の観点を交えて、従業員持株会との賢い付き合い方を解説します。
従業員持株会とは
従業員持株会は、従業員が自社の株式を定期的に購入し、資産形成を図る制度です。会社側にとっては、従業員の会社に対する帰属意識を高め、安定株主を確保する目的があります。従業員側にとっては、給与天引きで自動的に積み立てができ、少額から自社株投資を始められる資産形成の仕組みとして機能します。
具体的な仕組みはシンプルです。毎月の給与から一定額が天引きされ、その資金で自社株を購入します。購入方法は市場での買付や第三者割当などがあり、会社によって異なります。重要なのは、多くの企業が「奨励金」を上乗せしてくれる点です。

なお、この制度は上場企業だけのものではありません。非上場の中小企業でも従業員持株会を導入しているケースがあります。特に、経営者の高齢化が進む中小企業では、事業承継対策の一環として活用されることもあります。株式を分散させることで相続時の課税評価を抑えたり、後継者への株式集約をスムーズに進めたりする目的です。このように、従業員持株会は企業規模や上場・非上場を問わず、多様な目的で活用されている制度なのです。
高い普及率と手厚い支援
従業員持株会は、多くの企業で採用されている制度です。東京証券取引所の2023年度調査によれば、上場企業3,932社のうち3,273社(83.2%)が従業員持株制度を導入しています。つまり、上場企業の8割以上が採用しているメジャーな福利厚生制度なのです。
さらに注目すべきは奨励金の手厚さです。同調査によると、従業員持株会を実施している企業の96.6%が奨励金制度を採用しており、平均支給額は拠出金1,000円あたり99.79円(約10%)に達しています。最も多いのは100円(10%)の支給で、全体の40.9%を占めます。中には、100%の奨励金を支給している企業もあります。業種別では情報・通信業が最も高く、平均134.77円(約13.5%)となっています。
それでは、「10%の奨励金」とは何を意味するのでしょうか。毎月1万円を拠出すると、会社から1,000円が上乗せされ、実質11,000円分の株式を購入できることになります。つまり、拠出した時点で即座に10%も資産が増える計算です。これは預金や投資信託では得られない、従業員持株会ならではの大きなメリットと言えます。
従業員持株会のメリット
従業員側のメリットは以下の通りです。
- 少額から投資可能:通常、株式投資には数万円から数十万円の資金が必要ですが、持株会なら月々数千円から始められます。
- 奨励金による資産増:前述の通り、平均10%程度の奨励金は大きな魅力です。仮に株価が横ばいであれば、この分だけ確実に資産が増えることになります。
- 自動積立の仕組み:給与天引きのため、意識せずに継続できます。「先取り貯蓄」の効果が期待できます。
企業側のメリットも無視できません。従業員のモチベーション向上、安定株主の確保、敵対的買収への防衛効果などが期待できます。
見逃せないデメリットとリスク
一方で、強調したいのは従業員持株会特有のリスクです。最大のリスクは「集中投資」です。資産運用の基本原則は「分散投資」ですが、従業員持株会は自社株のみに投資する制度です。
これは何を意味するのでしょうか。勤務先の業績が悪化した場合、給与やボーナスが減少するだけでなく、保有する自社株の価値も同時に下落します。最悪のケースとして会社が倒産すれば、職と資産を同時に失うことになるのです。

その他にも、すぐに換金できないという「流動性の低さ」などのデメリットもありますが、集中投資のリスクが最も重要なデメリットです。
東京電力の事例が教えてくれること
集中投資の危険性を示す典型的な事例が、2011年の東日本大震災時の東京電力株です。震災前日には2,100円を超えていた株価は、原発事故を受けて暴落し、2012年7月には120円まで下落しました。これは震災前から90%以上の下落を意味します。

東京電力は震災前、誰もが知る大手電力会社であり、安定企業の代表格でした。配当利回りも高く、多くの従業員が持株会を通じて自社株を保有していたと考えられます。しかし、想定外の大災害により、その「安定」は一夜にして崩れ去りました。
ファイナンシャル・プランナーとして相談業務を行う中で、従業員持株会に集中投資をしている事例を時々見かけます。「うちの会社は安定しているから大丈夫」という言葉を耳にすることも多いです。しかし、東京電力の事例が示すように、どれほど安定的に見える会社であっても、将来何が起きるかは誰にも予想できません。自然災害、経営判断のミス、業界構造の変化、技術革新による淘汰など、リスクの種類は多岐にわたるのです。
株式投資の王道と比較してみると
集中投資のリスクをより明確にするために、分散投資の代表例と比較してみましょう。
現在、多くの投資家が積み立てている「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称「オルカン」)は、先進国・新興国を含む全世界約3,000銘柄の株式に投資しています。その内訳は時価総額比率で米国が約64%、日本はわずか5%程度です。

ここで考えていただきたいのです。世界約3,000社の中で、日本企業全体でもたった5%。その中であなたの会社は何%を占めているでしょうか?
仮にあなたの勤務先が日本を代表する大企業であったとしても、オルカン全体に占める割合は0.2%程度が最大です。例えば、保有資産の50%を従業員持株会で自社株を持つことは、世界分散投資と比較して250倍もの集中投資をしていることになるのです。
この比較から、従業員持株会に偏重することは、いかに極端な集中投資であるかが理解できるのではないでしょうか。

私が推奨する「奨励金を賢く享受する戦略」
従業員持株会について、私は積極的には推奨しない立場を取っています。理由は、資産運用の大原則である「分散投資」に真っ向から反するためです。
実は私自身も、FP事務所を兼業で運営しながら企業に勤める会社員として、従業員持株会を利用しています。ですから、この制度の魅力も課題も、実体験として理解しているつもりです。
しかし、平均10%程度という奨励金の魅力は無視できません。そこで私が実践し、お客様にも提案しているのが、「売却可能単位になったら都度売却する」という戦略です。これは、奨励金のメリットを最大限享受しながら、集中投資リスクを最小化する方法です。
具体的な実践方法
- 毎月一定額を持株会に拠出:奨励金を受け取る(例:月1万円拠出で約1,000円の奨励金)
- 売却可能な単位に達したら速やかに売却:株式を証券口座に引き出し、市場で売却
- 売却代金を分散投資へ:NISAやiDeCoを活用した投資信託による分散投資に振り替え

この戦略の優れた点
- 奨励金分は利益確定:約10%の上乗せ分をできる限り株価変動リスクにさらさずに確保
- 集中投資リスクの回避:自社株の保有期間を最小化し、「勤務先と資産の連動」を防ぐ
- 心理的負担の軽減:業績悪化時でも、仕事と資産の両面でダメージを受けることを回避
- 真の分散投資を実現:売却資金で国内外の株式・債券に幅広く投資できる
実践時の注意点
この戦略を実行する際は、いくつか留意すべき点があります。
まず、会社によっては売却に一定の制限(引き出し可能なタイミングや単位)がある場合があるため、事前に持株会の規約を確認しましょう。また、会社の重要な未公表情報を知り得る立場にある方は、インサイダー取引規制に抵触しないよう、売却時期には十分な注意が必要です。
税務面では、課税口座での売却となるので売却益に対して約20%の税金がかかります。しかし、売却タイミングを分散することで株価の値動きの影響を小さくできるので、奨励金分のメリットを得られる可能性が高いでしょう。
他の選択肢
もちろん、この戦略だけが正解ではありません。会社の将来性を信じて長期保有する選択肢もあります。その場合でも、金融資産全体に占める自社株の割合を大きくし過ぎないことをお勧めします。
また、ライフプランとの兼ね合いも重要です。住宅購入や子どもの教育資金など、大きな支出予定がある場合は、持株会への拠出額自体を調整することも検討しましょう。
まとめ
従業員持株会は、平均10%程度の奨励金という魅力的なメリットがある一方で、集中投資による大きなリスクも抱えています。
私は「売却可能単位に達したら都度売却し、分散投資に振り替える」という戦略を推奨します。これにより、奨励金のメリットを享受しながら、集中投資リスクを最小化できます。
資産形成において重要なのは、一つの手段に依存せず、リスクとリターンのバランスを考えながら、ご自身に合ったポートフォリオを構築することです。従業員持株会は、その選択肢の一つとして賢く活用していきましょう。
参考資料
- 東京証券取引所「2023年度従業員持株会状況調査結果の概要」(2025年2月21日発表)
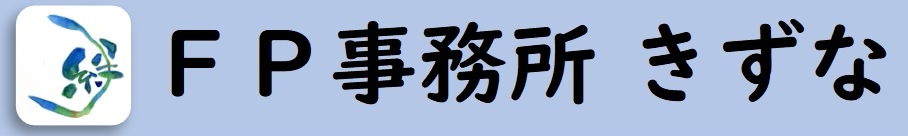



コメント