NISA口座で保有している商品のコストがいくらか、ご存知ですか?
あなたがNISA口座の中で500万円を信託報酬1.0%の投資信託で運用していると想定してみてください。支払うコストは年間5万円です。一方、信託報酬0.1%の同じタイプの商品なら年間5,000円で済みます。その差は年間4.5万円、10年で45万円、20年で90万円にもなります。
このようなコストを意識していない方は多いです。一方で、「もっと低コストの投資信託を買いたい」「この金融機関には欲しい商品がない」と感じていても、「NISAは一人一口座だから仕方ない」と諦めている方も多いです。
実は、NISA口座の金融機関は変更できます。しかし「一度開設したら変更できない」「変更すると今の商品を売らなければならない」という誤解から、不満を抱えたまま投資を続けている方が少なくありません。今回は、この『一人一口座』の本当の意味と、金融機関変更の正しい知識をお伝えします。
驚くべき金融機関によるコスト差
金融機関によって取り扱う商品のラインナップは大きく異なります。特に信託報酬の差は、長期投資において無視できない影響があります。
例えば、米国株式に投資する同等のタイプの投資信託を比較してみましょう。

A銀行(対面型金融機関)で多く販売されている商品
・商品名: ○○米国株式ファンド
・信託報酬: 年1.65%程度
・500万円保有時の年間コスト: 約82,500円
B証券(ネット証券)で人気の商品
・商品名: eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・信託報酬: 年0.09372%
・500万円保有時の年間コスト: 約4,700円
この例では、年間約7.8万円、20年間で156万円もの差が生まれます。同じ米国株式市場に投資しているにもかかわらず、商品選択だけでこれほどの差が出るのです。
ネット証券を中心に、近年は超低コストの投資信託が充実してきました。しかし、開設時に選んだ金融機関のラインナップが限られている場合、こうした選択肢にアクセスできないケースがあります。
『一人一口座』という言葉がわかりにくい。よくある誤解
誤解①「一度NISA口座を開設すると金融機関を変更できない」
これは最も多い誤解です。「一人一口座」とは、「その年に取引できるNISA口座は一つの金融機関に限られる」という意味であり、金融機関を変更できないという意味ではありません。年単位で金融機関を変更することが可能です。
制度上は、2024年にA証券、2025年にB証券、2026年に再びA証券、といったように毎年変更することも可能です。ただし、実務的には頻繁な変更は管理が煩雑になるため推奨できません。
過去にA証券で購入した商品は、B証券に変更した後もA証券の口座内に残り続けます。非課税保有期間(つみたて投資枠・成長投資枠ともに無期限)も継続され、売却時の利益も非課税のまま受けられます。

誤解②「変更すると過去に購入した商品を売却しなければならない」
ただし注意が必要なのは、商品そのものを新しい金融機関に移し替えることはできないという点です。もし新しい金融機関で同じ商品を保有したい場合は、旧口座で一度売却し、新口座で買い直す必要があります。
誤解③「変更すると生涯投資枠(1,800万円)が減る」
生涯投資枠は、どの金融機関で投資したかに関係なく、投資総額で管理されます。A証券で500万円、B証券で300万円投資した場合、合計800万円が生涯投資枠から消費されたことになります。金融機関を変更しても、この枠が減ることはありません。
誤解④「一度変更したら、元の金融機関には戻れない」
これも誤解です。再度変更手続きをすれば、以前利用していた金融機関に戻ることも可能です。ただし、その年に新しい金融機関で買付をしていないことが条件となります。
誤解⑤「変更手続きは複雑で時間がかかる」
手続き自体は、変更先の金融機関に申し込み、変更元から「勘定廃止通知書」を取得して提出するという流れです。ただし、手続きには2週間から1ヶ月程度かかり、その間は新規買付ができないため、タイミングには注意が必要です。

金融機関変更のメリット・デメリット
金融機関変更のメリット
- 商品ラインナップの充実した金融機関を選べる(特にネット証券は低コスト商品が豊富)
- より低い信託報酬の商品に乗り換えられる
- 取引ツールやサービスの優れた金融機関を利用できる
- ポイント還元などの特典が充実した金融機関を選べる
金融機関変更のデメリット
- 過去の商品と新規購入商品の管理が複数の金融機関に分散される
- 変更手続きに2週間〜1ヶ月程度かかり、その間は新規買付ができない
- 複数の金融機関の管理が必要になる
デメリットはあるものの、長期投資において商品選択の自由度とコストは非常に重要です。現在の金融機関のラインナップに不満がある場合は、変更を検討する価値があります。
変更手続きの注意点

金融機関を変更する際は、以下の点に注意しましょう。
1. タイミング: その年に一度でも買付をしていると、変更は翌年からの適用となります。年内に変更したい場合は、買付をする前に手続きを開始してください。
2. 手続き期間: 9月末までに変更手続きを完了すれば、その年から新しい金融機関で取引できます。10月以降の変更は翌年からの適用となります。手続きには2週間〜1ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請しましょう。
3. 勘定廃止通知書の取得: 変更元の金融機関から「勘定廃止通知書」を取得する必要があります。この書類を変更先に提出します。金融機関によっては発行に時間がかかる場合があるため、早めに依頼しましょう。
4. 複数口座の管理: 変更後も、旧金融機関の口座は残り続けます。ログイン情報を保管し、定期的に資産状況を確認しましょう。
5. 積立設定の再設定: 積立投資をしている場合、新しい金融機関で改めて積立設定を行う必要があります。旧金融機関の積立設定は自動的に引き継がれません。
まとめ
「一人一口座」という原則は、同時に複数の金融機関でNISA取引ができないというだけで、金融機関の変更を禁じるものではありません。過去の商品の税制優遇を維持したまま、より良い環境で新規投資を続けることができます。
まずは、現在保有している商品の信託報酬を確認してみてください。年間いくらのコストを支払っているのか、より低コストの選択肢はないのか、一度見直すことをお勧めします。
現在の金融機関のラインナップや手数料に不満がある方は、金融機関変更を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、変更のタイミングと手続きには注意が必要です。
長期投資において、わずかなコスト差が将来大きな差となります。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
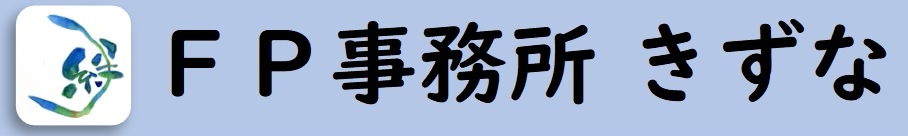



コメント